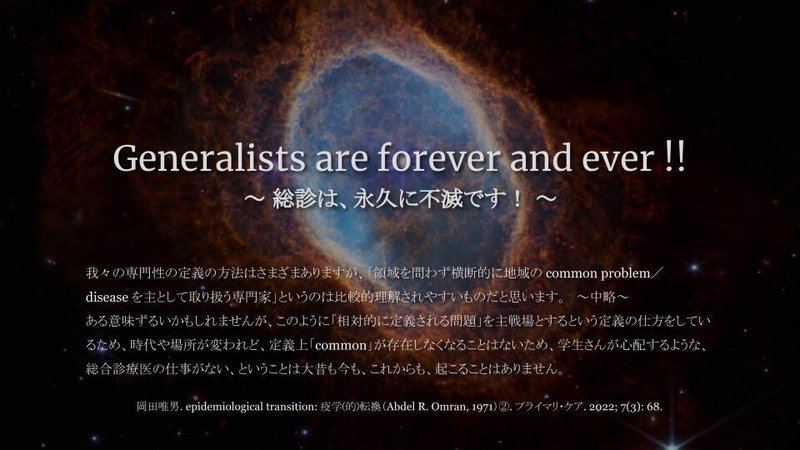お産がとれる家庭医になるために
コトクは今週末は大阪で産婦人科専門医試験でした。
五島列島で総合診療して、3ヶ月オーストラリアのへき地、離島医療の旅をしたので、2年同期たちから遅れて産婦人科専門医試験になりました。
でも、全然回り道とかじゃなくて、全てが繋がって今の自分がいるんだなあと感じています。お産がとれる家庭医までもう少し。
筆記試験は難しかったのですが、面接は周産期も腫瘍も不妊も内分泌どの分野も奄美大島でやってきたことだったので、改めて「この道は間違ってなかった」と思えるものでした。

奄美大島では産婦人科医として、お産も、癌の予防、診断、化学療法から緩和ケア、人工授精までの不妊治療、月経困難症から更年期障害、子宮脱などの女性のヘルスケア、緊急疾患の搬送など全てを学ぶことが出来ました。
結果は10月頃になりますが、どうか受かってて欲しいです。
専門医になれば産婦人科医のいない島に妊婦健診いったり、1人で頑張ってる産婦人科の先生のお手伝いができたり、学校で性教育ができるかもしれない。
改めて、自分を育ててくれて部長やまわりの助産師さん、スタッフの皆さんに感謝申し上げます。
とゆうことで、また色々活動を再開していきます!
来月8月12日は商店街のお祭りがあるので、奄美暮らしの保健室もわたあめ配ったり、アイスコーヒー配ったりするので、是非遊びにきてください!!

奄美暮らしの保健室が発酵してきました。
奄美暮らしの保健室も今回で3回目になります。
9月はなんとGlocaLandの医学生や看護学生、獣医学生、研修医のみんなが東京、大阪、名古屋、沖縄と各地から暮らしの保健室をするために奄美まで来てくださいました!

その際に奄美の地元の新聞で一面で取り上げていただきました。

くらしの保健室の役割は医療者を病院の外に連れ出すこと、医療者が街の人と白衣を脱いで交流すること、対話すること。
とコトクは考えています。
コロナ禍で断ち切られた、人と人との繋がりを取り戻すことで、孤独を無くし、社会のつながりを強くするまちづくりの一環で、僕たちは「社会的処方」と呼んでいます。
病院や薬で治せない、孤独という社会の病を治すこうした活動のことを「社会的処方」と言って、日本全国でも広がっています。
イギリスの家庭医の先生は実際に病院で「社会的処方」を診療行為としてできます。
例えば、孤独な高齢者をアート教室につないだり、美術館のチケットを処方したり、いろいろな活動があります。
この暮らしの保健室はシンプルに街中でコーヒーを配る活動で資格がいらない、誰でもできる社会活動です。
それこそ研修医や看護学生、高校生でもできます。
街のために何かしたいって気持ちを持った人沢山いると思うんです。その人たちの最初の一歩になれば良いなと思って活動を続けてます。
コトク家も2年前に奄美にきて、ちょうどその時娘を県病院で出産しました。
コロナで子供を連れて行く公園や図書館が閉鎖されていたり、母子で活動できるママクラスみたいなのが軒並み中止になって、ずっと家族だけで過ごすことが多かったです。
そんな時に商店街のピアノで娘が遊んでいる時に商店街のおばあちゃんやおじいちゃん達がよく娘に話しかけてくれて、可愛がってくれて、時にはおじいちゃんが三線をひいて島唄を歌っていて、この商店街に精神的に助けられた気がします。
だからピアノの前で、この商店街でいつか暮らしの保健室をやりたいなと思ってました。
こうして実際にピアノの前で活動できて、今度は自分が人と人を繋ぐ立場になれて幸せです。

実際に街に出てみて、月経の悩み、将来の不安、家族の健康相談などをさせていただました。暮らしの保健室は診療行為は出来ないですが、「それは病院に行ったほうがよいのか」を伝えることができます。重症化する前に受診することで、予防医療にもなるのかなと考えています。
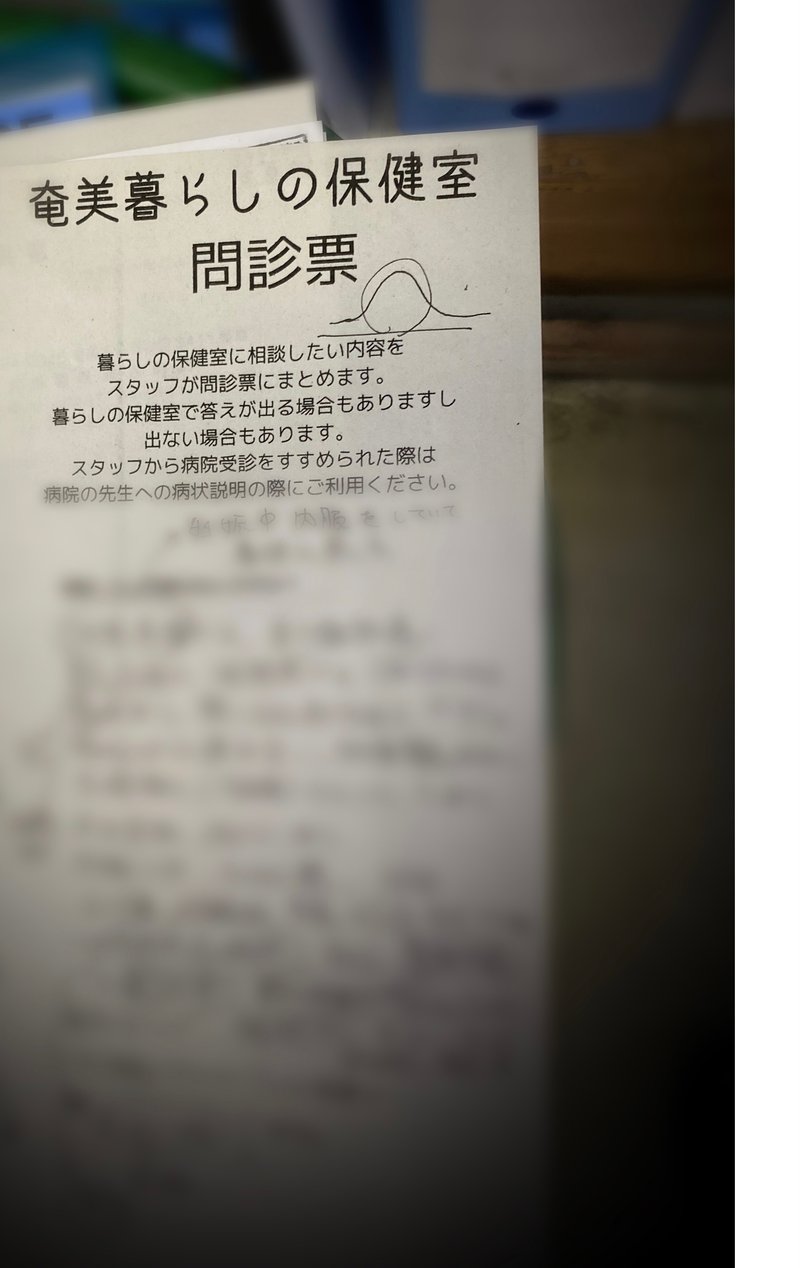
奄美はドクターヘリが入り急性期の医療は強くなったと思います。なので、僕たち暮らしの保健室は予防医療だったりプライマリケアといったもっと医療の根本となるところで離島医療の助けになればと思い、細く長く活動を続けられたらと思っています。
こんな暮らしの保健室が奄美のあちこちで広がっていたったら幸せです。
これからも奄美暮らしの保健室をよろしくお願いします。

宇宙飛行士試験に落ちました〜究極のへき地医療は宇宙医療だ〜
こんにちは!奄美大島でお産がとれる家庭医(へき地総合診療医)を目指して修行中のことくと申します!
表題にある通り、ことくは宇宙飛行士試験に落ちました。
落ちるどころか、書類審査で箸にも棒にも引っ掛かりませんでした。
なんとなく最近気持ちの整理がついたため記事を書いておこうと思いました。
そもそも何で離島の産婦人科医が宇宙を目指すのか?
単純に宇宙が魅力的すぎるからです。

だって、このポスター最高に魅力的じゃないですか!!
え?宇宙飛行士になれるの?13年ぶりに募集?次に募集が来るのいつかわからない?
受けるしかないでしょ。
でも、何ページもあるエントリーシートや健康診断書の書類作成をしていると何度も「どうして宇宙飛行士を目指すのか」と自問自答することになります。
JAXAの偉いひと「コトクさんはどうして宇宙飛行士を目指すのですか?」
コトク「、、あのー、それは、、かっこいいから?」
まあ、絶対落ちますよね。
申込してから色んな宇宙の本を読んだり、NASAのラジオを聴いて、宇宙についてお勉強していると段々、へき地総合診療医の自分が宇宙を志す「理由」が出てきました。
Houston We Have a PodcastNASA.gov brings you the latest images, videos and news from Awww.nasa.gov
オーストラリアには宇宙を目指すへき地で戦える総合診療医の先生がいる。
日本も離島、へき地で戦う総合診療医の先生はいるが、オーストラリアのRural Generalistは「へき地度」が凄すぎる。
南極の真っ白な氷の上で「へき地医療さいこーーー!!」って叫んでるぶっ飛んでる先生がいたり
電気もガスもないパプアニューギニアの小さな島から島をわたり「さあ、今日の離島医療はここだー!」と医療支援をしている先生がいて
そんな中でゲネプロの齋藤先生の本に出てくる
へき地医療をめぐる旅ー私は何を見てきたのだろうか https://amzn.asia/d/aY0nNiC
「南極?いやいや究極のへき地は火星さ!」
と豪語するへき地総合診療医の先生がいました。
「これだ!コトクと宇宙の繋がりはここだ!」
火星移住計画が進む中、いつか誰かが宇宙ではじめて出産する時が来る。

それは経膣分娩なのだろうか?帝王切開なんだろうか?
それを介助するのは産婦人科医だろうか?ロボットだろうか?助産師さんだろうか?お産がとれる家庭医だろうか?もしくは遠隔医療を駆使する宇宙飛行士だろうか?
宇宙線の妊娠中の影響は何だろうか?
誰がはじめて宇宙で出産するんだろうか?
When will the first baby be born in space?theconversation.com
どんどん妄想が膨らみ宇宙で最初にお産をとるのは自分しかいないと信じ込んだところで
書類選考で落ちました。

最初は思いつきで、ダメもとで申し込んだ宇宙飛行士試験でしたが、落ちたらやっぱりめちゃくちゃ悔しかったです。
時間があったらpodcastで宇宙の話を聴いて、火星計画の本の話を読んだりしてたりして、、、でも、そんな知識も使うことなく書類選考で落ちてしまいました。
しばらく放心状態で「あー自分は宇宙飛行士試験落ちたのかー」と思ってましたが、逆にこの自分が宇宙飛行士を目指していたのかと考えると面白くて、笑ってしまいました。
「あー、いい夢を見たな」とそう思えるようになりました。
そして、JAXAが、人類が、まだ火星に行ってないから、コトクを採用するのはまだ早いと思われたんだ、とそう思うようになりました。
いつか、JAXAに「Dr.コトク、今度火星で出産する妊婦がいるみたいだから今度のフライトで飛んでくれるか?」と言われるくらい「どんなへき地でもお産がとれる総合診療医」として修行しようと再決心した次第でした。
人が住むところに病あり
病あるところにジェネラリストあり
Generalists are forever and ever!!
総合診療は永久に不滅です!
ーー岡田唯男先生